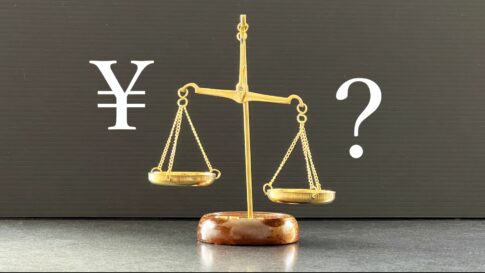SalesNowの調べによると2024年に東京都の起業数は44,009件となっています。ひと昔前と異なり、フリーランスやひとり法人など様々な働き方が増えており、2025年も都内で開業創業する人は引き続き多い傾向だと考えられます。
ただし起業には大きな金銭的な負担もあります。法人の設立費用、従業員の人件費・社会保険料、事務所や店舗の初期費用に毎月の家賃、PCや機械設備、消耗品、営業ツール等…
これら費用負担が重いため、起業の時期をずらしたり諦めたりする人もいます。
しかし諦める前にぜひ「創業助成事業」を検討してみてください。東京都では創業予定者や創業まもない個人法人を支援するために、東京都と公益財団法人東京都中小企業振興公社が提供している「創業助成事業」があります。創業初期に必要な経費の一部を400万円を上限に助成する制度です。この助成金は開業届を提出する前や法人設立前に応募することができます。
本記事では、創業助成事業の概要や審査のポイント、その活用方法について詳しく解説します。
参考:創業助成事業ホームページ
1. 創業助成事業とは
創業助成事業は、東京都内の開業率向上を目的として、都内で創業を予定している個人や、創業から5年未満の中小企業者等に対し、創業初期に必要な経費の一部を助成する制度です。これにより、創業者の資金的負担を軽減し、事業の安定した立ち上げを支援することを目指しています。
例年毎年4月と10月の年2回募集があり、令和7年も同様に公募が予定されています。
2. 創業助成事業の対象者
創業助成事業の対象者は、以下の条件を満たす方々です。
- 都内での創業を具体的に計画している個人:東京都内での創業を予定しており、具体的な事業計画を持っている方。
※創業前の個人の場合は交付決定後速やかに開業し、開業届等を提出することが必要です。 - 創業後5年未満の中小企業者等:法人の場合、法人の代表者の経営経験が5年未満で、本店所在地が都内にあること。個人事業主の場合、開業届出から5年未満で、主たる事業所が都内にあること。
また、申請時点で17項目ある各種創業支援事業のうちいずれかの事業を終了・完了していることが必要です。以下17項目の創業支援事業を列挙します。そのうち太字で書かれているものが比較的要件を満たしやすいものですので確認してください。
- ①TOKYO創業ステーション等の公社創業支援課の事業計画書策定支援を修了した方。
- ②TOKYO創業ステーション等の公社創業支援課の東京シニアビジネスグランプリのファイナリストに進んだ方
- ③公社経営戦略課にて事業可能性評価事業で「事業の可能性あり」と評価され、継続的支援を受けている方
- ④公社経営戦略課にて商店街開業プログラム(商店街起業促進サポート事業)の受講を終了した方
- ⑤都内創業支援施設に入居している、又は入居していた方
- ⑥青山スタートアップアクセラレーションセンターにてアクセラレーションプログラムを受講している、又は受講していた方
- ⑦東京都のTCICアクセラレーションプログラム又はTCIC ldeation Programに採択された方
- ⑧東京都のTOKYO Co-cial IMPACTスタジオプログラムに採択された方
- ⑨東京都のTOKYO STARTUP GATEWAYのセミファイナリストまで進んだ方
- ⑩東京都女性ベンチャー成長促進事業(APT Women)の国内プログラムを受講している、又は受講していた方
- ⑪女性・若者・シニア創業サポート事業、女性・若者・シニア創業サポート2.0の融資を利用し、証明を受けた方
- ⑫信用保証協会の保証を受けた創業融資を受けた方
- ⑬東京都出資のベンチャー起業向けファンドから出資を受けた方
- ⑭資本制劣後ローン(創業)を利用した方
- ⑮認定特定創業等支援事業による支援を利用した方
- ⑯認定特定創業等支援事業に準ずる支援を利用した方
- ⑰高校生企業家要請プログラム(起業スタートダッシュ)において、養成講座を修了された方。
これらの要件を満たすためには、概ね2か月以上の準備期間が必要となるため、早めの行動が求められます。
また、同じ東京都中小企業振興公社が行っている、「商店街起業・承継支援事業」「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」を受けていた場合、今後受ける予定の場合は申請することはできません。
また、個人で助成金に採択された場合、助成対象期間中に法人成りする場合は様々な条件を満たす場合があります。個人で申請する場合はしばらく法人成りは控えた方がよいでしょう。
3. 創業助成事業の助成額と助成率
創業助成事業の助成内容は以下のとおりです。
- 助成限度額:上限400万円、下限100万円。
- 助成率:助成対象経費の3分の2以内。
例えば、対象経費が600万円の場合、その3分の2である400万円が助成されます。ただし、次で解説する助成対象経費のうち、事業費及び従業員人件費を対象経費とする助成金限度額は300万円。そして委託費を助成対象経費とする助成金限度額は100万円とし、その2つを合計したものが400万円となります。
4. 創業助成事業の対象経費
助成の対象となる経費は、以下の項目です。
【事業費】
- 賃借料:事務所や店舗などの賃貸費用。交付決定前に契約して継続して使用している物件も可。助成対象期間中のもの(最長で交付決定から2年)
- 広告費:販路開拓や顧客獲得を目的とした広告宣伝費用。広告の掲載費やパンフレット等のデザイン製本費、ホームページの制作費等。
- 器具備品購入費:事業運営に必要な機器や備品の購入費用。机、PC、コピー機、エアコン等
※補助金助成金の中では珍しくPCやタブレットが対象になります。 - 産業財産権出願・導入費:特許や商標などの出願・導入にかかる費用。
- 専門家指導費:事業運営に関する専門家からの指導・助言にかかる費用。創業助成金の申請代行費用や、税務に関する税理士費用、法務に関する弁護士費用、法人設立に伴う司法書士費用等は対象外です。
- 従業員人件費:従業員の給与や賃金。
- 市場調査・分析費:市場調査や分析を外部に委託する際の費用。
【従業員人件費】
- 従業員人件費:従業員の給与や賃金。交付決定日よりも前に雇用した方も対象となります。正規従業員の場合は35万円/月。パートアルバイトの場合は8,000円/日が上限となります。
【委託費】
- 市場調査・分析費:市場調査や分析を外部に委託する際の費用。コンサルティングに係る経費は専門家指導費となり明確に区分することが必要です。
5. 審査のポイント
創業助成事業の審査では2回に分けて審査が行われます。まず最初の審査が書類審査。提出された事業計画書を元に審査を行います。その後面接審査を経て、書類審査、面接審査の内容を総合的に考慮して採択を決定します。
ここでは、書類審査の重視されるポイントについて解説します。
- 製品・商品・サービス内容の完成度:具体的な内容、適切な価格設定、実施する時期や場所等について説明できているか。
- 問題意識・潜在力の明確さ:創業によって解決可能な社会課題、経営理念、ビジョンが明確になっているか。事業に活かせる自分の強み・弱みと、その補強方法が明確になっているか。
- 対象市場に対する理解度・適応性:想定顧客が明確になっているか。対象市場の規模、特徴、成長性を的確に把握しているか。競合他社との差別化、優位性が明確になっているか。
- 事業の実現性:収益獲得の仕組みが適正であるか。製品・商品・サービスの製造・調達ルートが適格に設定されているか。販売戦略が適格であるか。想定されるリスクとその回避方法が検討されているか。
- 助成金の活用方法の有効性:事業への助成金の活用方法が事業の拡充等に効果的であるか。
- スケジュール・経営見通しの妥当性:経営計画・経営見通しが実現の見込める内容であるか。
- 資金調達の妥当性:助成対象期間中に必要な資金調達が見込めるか。助成金の交付がない場合でも、事業継続が可能な収支計画であるか。
- 申請経費の妥当性:事業計画に必要な経費が計上され、販売計画や経営計画と連動しているか。
これらのポイントを踏まえ、しっかりとした事業計画書を作成することが重要です。
6. スケジュールと応募方法
令和7年度第1回の募集スケジュールは以下のとおりです。
- 申請受付期間:令和7年4月8日(火)~4月17日(木)必着。
- 書類審査結果通知:令和7年6月中旬頃
- 面接審査:令和7年7月3日(木)~7月10日(木)
- 面接審査結果通知:令和7年9月上旬頃
応募方法は電子申請と郵送申請の2種類が選択できます。
まとめ
創業助成事業は創業初期の資金面に不安を抱える時期にとってとても役立つ助成金のひとつです。店舗家賃、従業員人件費、さらにはPCやタブレットも補助対象になる等、補助対象が広い点もうれしいところです。
しかしその分事業計画を考えたり書類をそろえたりするのは中々難しい助成金です。検討する際には過去の採択事例等を参考に自社がやろうとしているサービスが過去の採択事例と比較してどの程度インパクトを与えることのできる事業なのかぜひ検討してみてください。
そして不明な点があれば当事務所のような認定支援機関にお気軽にお問合せください。